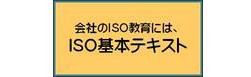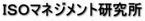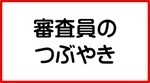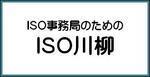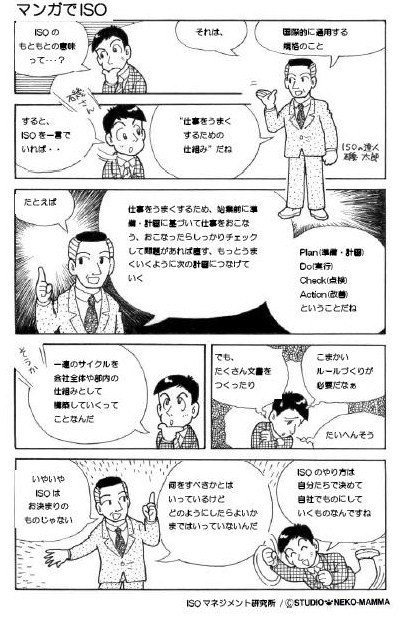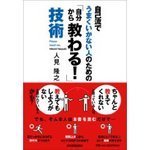先日、JRCA(マネジメントシステム審査員評価登録センター)が主催した、審査員向け講演会に参加しました。その中で、興味深いデータが公開されました。
そのデータとは、組織がISOを取得して、
6年の間は、ISO認証を返上する率が高いが、
それ以降は、率が減り、取得して9年を
超えると、ほとんど返上する組織はないと
いうデータです。
6年というと、更新審査の2回目の
時期であり、組織としては、
ISOの費用対効果もだいぶ見えて
くる時期です。
このように、
返上する判断基準としては、
ISOの費用対効果という話が
よくあがります。
しかしながら、
ISOの認証を維持するかどうかの
判断は、これだけでは、不十分だと感じます。
つまり、
費用対効果という判断基準だけではなく、
それ自体の取組みに意味や、
責任、義務があるか、ということも
勘案して、判断すべきではないかと
考えます。
具体的にいいますと、
最近、食品廃棄物の不正や
杭打ち工事の偽装が問題となったように、
企業の不正や偽装、こういう問題は、
今後も必ず社会の話題にのぼることは
間違いありません。
こういうことが起きると、
必ずいわれることは何か、というと、
再発防止の取組みをしっかりしろ、
となります。
再発防止の取組みをしっかりするとは、
自社でできる限り一生懸命に行うといっても、
自社では限界がありますし、
やはり、しっかりやっていることの
説得力を出すには、利害関係のない外部から、
自社をチェックしてもらうこと、
第三者評価というものに行き着きます。
実際に、ISO/IEC17021では、
認証の最終的な目的は、
全ての関係者に、マネジメントシステムが、
規定要求事項を満たしているという信頼を
与えることである、と明記しています。
全ての関係者とは、以下になります。
1.認証(審査)機関への依頼者(組織)
2.マネジメントシステムが認証された組織の顧客
3.政府関係当局
4.非政府組織
5.消費者及び社会のその他の構成メンバー
今のISO業界を考えますと、
ISOの認証審査制度という仕組みや
実際の審査の質をどう担保するか、など、
まだまだ多くの課題があります。
しかしながら、
今の社会的状況を考えますと、
もはや第三者評価は、社会的な要請だともいえ、
このような機会をもっておくことは、
企業の大小を問わず、今の企業経営にとっては、
必須のことだと感じます。