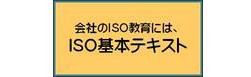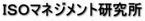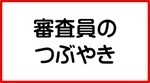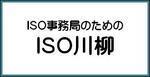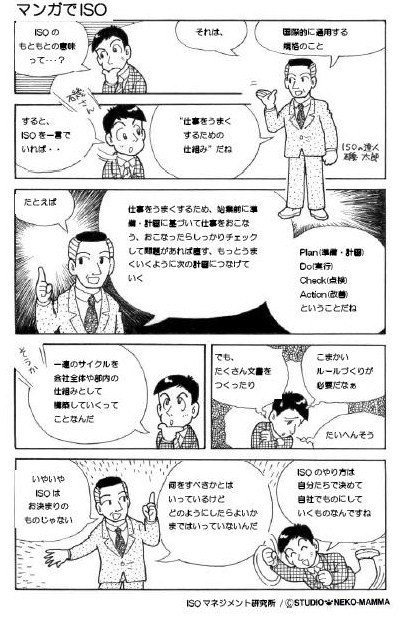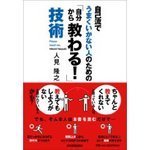先日、長年に渡ってISOを取得しているある組織からこんなことを聞きました。最近では、外部審査がマンネリ化していて、指摘は出ないか、出ても有意義なものは出ないという話を聞くことがありました。
ISOの外部審査は、当たり障りのない程度のもので良いと考える組織にとっては、特に問題としないことなのかもしれませんが、外部審査で改善のきっかけ作りを図りたいと考えている組織にとっては悩ましい課題となります。
そのような悩みを持つ組織は、どのようにしたらよいかですが、一度、審査機関に相談してみる、要望してみるというのも一つの方法ですが、ズバリ、審査機関を変更してみることも有効だと感じています。
実際に、ある組織では、3年ごとに審査機関を変更し、組織の改善力を図っているという組織もあります。
では、審査機関を変更する際に、どの審査機関を選んだらよいかということですが、審査費用だけでなく、審査機関がどの程度、ISOに関する情報発信をし、工夫しているかを判断材料とするとよいと思います。
例えば、ISOのセミナーなどを開催し、情報提供に熱心なところや、受審組織のモチベーションを保つために、表彰制度を設けたりするところなどもありますので、このような情報は、審査機関のホームページを見れば、おおよそのことがわかります。
もちろん、肝心の審査の質も大事になりますが、こちらは、審査機関というより実際に担当する審査員によって異なってきますので、審査機関ではなく、審査員次第というのは実際にところだと思います。
担当となる審査員は、実際に受審してみないとわからないのですが、ある審査機関では、審査機関移転時の審査では、評価の高い審査員をあえて割り当てるというところもあります。
あとは、審査費用の問題ですが、感覚としては、審査機関の認定機関がUKASであると費用が軽減されている傾向にあると感じますが、審査機関によって、異なっているのが現状です。
審査機関は、当初、私がISOのコンサルを始めた23年くらい前と比べ、だいぶ様変わりしています。ISOは活用してなんぼであると考えれば、審査機関も活用してなんぼであるという気がしています。